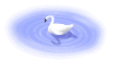神が神であるために

○ 一人になった時
死を前にして「人は徹底的に一人である」と言っていたお坊さんがいた。
私は決して自己中心ではない、周りのこともちゃんと考え、人とも仲良くやってきた。そう思っている人であっても、最後に行きつくところは「自分」である。自分が自分であることから離れられない。自分しか残らない。自分が出発点で、自分に帰ってきたのである。何を中心に生きて来たのか?
(心の中心に何があったのか)
自分に向き合わねばならない。一人になった時に「自分」だけが残る。あくまでも孤独である。
しかし、自分の思いではなく、神の愛に生きてきた人。
自分の中に神(愛)を宿し、「愛」を中心として生きてきた人。真に信仰を持ってきた人は、自分の中心に自分ではなく「神」がいる。愛が共にあって、愛に委ねてゆける。(我ならぬ我に委ねてゆける)
死を迎える瞬間、「すべてを御手(愛)にお委ねします」と言える人もいた。イエスがそうであった。
この違いは大きい。表面的に宗教を学び、信仰をよそおっていても、自分の中心は自分であることに変わりはないと言う人は、最後に一人になるだろう。しかし、心の中心に自分ではなく神をおいていた人、自分の思いではなく、神から来た「愛」によって生きてきた人は、愛とともに最後まで歩む。神に委ね、神(愛)のもとに帰る。
願わくは、後者のような信仰を持ちたいものだ。
一人になった時、自分しかないという人は可哀そうな人である。神がともにいる、「愛」がある、と思える人は幸いである(安らかである)。愛にゆだねて、愛になり切ればいい。
愛として生きる為には一人ではいけない。神がともにいなくてはいけない。神も一人では愛になり切れないので人を求めたのである。愛とはそういうものである。

○ 一人であって一人でない
人間は二重的(二重構造の)存在、一人であって一人でない。
内に神を宿す存在、自分は空でも内には無限の愛を秘める存在。自分は無でも内には永遠の真理を宿す存在なのである。有限でありながら無限性を秘めている。永遠の中を生きている。
神と我は、二でありながら不二である。愛として一体である。常に対話(祈り)があり、涸れることのない泉の如く愛が溢れる、愛がある存在なのである。神から生まれ、愛から出発しているがゆえに、最後も神とともにあり、神のもとに帰る。愛は永遠である。
※
涸れることのない泉のような愛・・・これだけでエントロピー増大の法則を克服している。
私は私であって私でない。神を宿し、神であると言えるが、神ご自身ではない。神と私はともにあって愛なのである。イエスはこういったことを言いたかったに違いない。
○ 神のとらえ方
神は「はじめ」であり、「有って有るもの」であり、「一」なるお方である。
なにから始まったのかといえば、愛から始まったので、神のことを「愛」だと言う。
究竟なる存在、神というものを仏教的な表現で言うと、「即」であり、「如」である。
「即(そく)」とは「すなわち」であって、間髪を容れぬ直下の意である。一元を示す言葉である。「即」に成仏がある。人が仏に結ばれる幸を説くのが「即」である。
「如(にょ)」は「ごとし」であり、何ものかの指示であり、暗示である。不変不動を意味する。大元にある本有の性を示している。「如」はまた「一」である、「一」はまた「不二」ともいう。
あらゆる仏法は「不二の法門」に行きつく。不二とは、ものが未だ二つに分かれないそのままの様を指す。
この世は二元(相対・対比)、「二」の世界、人の愛は相対的なものであり背後に憎をはらんでいる。自と他、善と悪、美と醜、生と死、「二」にある限り苦から逃れられない。
神の愛は未分の愛、不二の愛、全てを包み込む大元の愛なのである。万民によりそい、永遠に変わることがない。「一」に帰ることが救いであり、喜びと平安、浄土はそこにしかない。
不二の愛は、「二」にあったとしても、愛し合い「一」に帰る愛である。一つになることが幸福なのである。もともとは愛(未分の愛)しかなかったのだから、愛に帰ることができる。
以上は、柳宗悦から学んだことである。

○ 私を受け止める為に
私はなぜ存在するのか?
私を受け止めることの出来る唯一の方法が、神との関係を理解すること、神の愛に帰結するということ。原因(存在の理由)に帰ること以外、自分自身をどうすることもできない。
自分だけを見たなら、むなしい、訳の分からない存在である。欲望を満たしたところで何にもならない。自分で自分に理由付けしたところで意味がない。人が考えるところの哲学は虚しいだけである。私自身に答えはない。「愛」に答えを求め、愛に委ね、愛とともに生きるしか道はない。
私が私をゆだねることの出来る唯一のものが「愛」なのである。だからそこに私と私の人生は完結する。
神を感じとり、愛に答えを見いだすしか、自分についての答えは見つからない。私を受け止め、私を生かし、私をゆだねることの出来るものは、「愛」以外にないのである。だから、神は愛であり、永遠なのである。
○ 私という存在
自分を造った(存在させた)のは自分ではない。自分ではないのに、自分だと思おうとするから不安になる。それは嘘だから。
神の愛より生まれてきたのだと信じれば救われる。神に委ねることができる。
愛が向かうところ(行先)は幸福だから、安心することができる。
見えない、聞こえないというだけで神を否定するのは大間違いだ。全ての存在はどこから来ているのか、その根底にあるものは愛ではないか。神とともに愛し、あとは信じていればいいのである。愛を信じるのである。(何もできないのに、自分が、自分がと思うから苦しくなる)
人間が、自力で幸せになろうとするには無理がある。(一歩先のこともわからない)
愛から生まれてきたものは、愛とともに愛して、愛のもとへと帰ってゆく。
愛のみが幸福を約束し得るのである。神は愛である。

○ 神が神であるために
神が神であるために、神が「愛」であるために、
愛の対象として人間をつくらざるを得なかった。愛を形にし、実現し、実感(体験)したかったのである。そしてその結論として、幸福に行きつかなくてはならない。永遠の喜びの中に生きたかったのである。
愛によって喜びをもたらすというのは、神の永遠を懸けたアイデンティティなのである。これは必ず果たされなければならない。神の絶対性と「愛」の名に懸けて実現されるべきことなのである。
愛の目的は果たされねばならない、人々は救われねばならないし、幸福は実現せねばならない。
神が神であるために、神が愛であるために、永遠をかけて、そのアイデンティティを守らなくてはならない。その約束は果たされなくてはならない。神の中においてそれは、永遠の時の中ですでに成就しているのである。
愛の約束は果たされなければならない、愛は成就せねばならない。「神が愛である」と言った以上、その愛は絶対的に機能せねばならない。愛を失うことは決してない。
愛が消失するということは、神が神でなくなるということだ。神を失うことは、全ての存在を失うことだ。
愛が不滅であるがゆえに、私がここに存在し、永遠の浄土が可能になるのだ。
「愛」は、うつろいゆく自分の思いではなく、神のものであるがゆえに、必ずその愛のもとに天国は築かれるのである。神が神であることを捨て、愛を捨てるということは絶対にない。私たちの歩みは、そのように神の愛に裏付けられたものなのである。
自分が今まで愛してきた(神とともに愛してきた)、体験してきた、その愛が強ければ強いほど、神への信仰は強固なものとなる。なぜなら、神は愛だからである。
悲しみが大きければ大きいほど、それを乗り越える「愛」はより深くなるし、神への理解、神への信仰も深まってゆくものなのである。神との絆も強くなってゆく。
神は神の名にかけて、永遠なる「愛」という存在をかけて、必ず人類を天国へと導かなくてはならないのである。

○ 仏が仏であるために
阿弥陀如来が如来であるために、法蔵菩薩の仏願はすでに成就しているのであり、不変のものである。道は開かれており、約束は果たされているのである。正覚を取ることにより真理は証明(確認)されている。
阿弥陀如来が、その如来の名に懸けて、無量の慈悲心にかけて、衆生を必ず摂取する(救いとる)のである。それは人が生まれる前から定められている。
浄土門の全ての教派は、法蔵菩薩が立てた第十八願(念仏往生の願)に全ての救いの根拠がかかっている。
「設し我れ仏を得たらんに、十方の衆生、至心に信楽して、我が国に生ぜんと欲して、乃至十念せんに、若し生ぜずば正覚を取らじ」と言う。
この願が、法蔵菩薩が正覚をえて阿弥陀如来となったことによって成就した。(法蔵菩薩が実在の人物かどうかはわからないが)このことは、仏の何たるかを証明している。この一文(本願)を典拠に、巨大な浄土宗や浄土真宗が建てられ、今も存続している。浄土真宗の信徒数は1500万人、日本最大の宗教団体となっている。
仏教の法典の数は膨大である。しかし信じがたいことだが浄土宗の裏付けとなっている法典の個所はこれだけ(無量寿経の第十八願)なのである。それしかない。仏が仏の名に懸けてこれをなすという。
語られていることが真理ならば、法蔵菩薩の実在の有無は問題とならない。
一つの真理を示すために、釈尊は法典を駆使する必要があったのである。(真理の確認のため)
「すべての衆生は阿弥陀仏(慈悲心)の名のもとに、必ず摂取される」という。仏が正覚をとることにより、この真理の絶対性を確認したのである。仏の慈悲心がいかなるものかを示したのである。
仏が仏であるために、この仏願は必ず果たされなければならない。否、すでにもう成就しているのである。
人は生まれた時からすでに、浄土に入ることを約されているのである。
柳宗悦は「人間の生まれるに先立ち、はや往生が決定されているのである。」と解釈している。
仏が仏である(無量なる慈悲のお方である)ということを伝えたかった。
そこに全ての衆生の救いがかかっている。仏の存在をかけて、宗門を建てたのである。
仏教は、仏が仏であること、すなわち「慈悲の心」に全てをかけているのである。
自身の内に住む仏が仏(慈悲)であるということに目覚めたのが「覚者」=悟りを開いた者であり、その慈悲の心に従って生きることを「成仏」を言うのではないか。そして仏の平安な心の中に生きていることを、「浄土」に生きるということなのではないでしょうか。

○ 自分の内側に何を見るか
「人は最後は徹底的に一人である」と言った以上、その一人となった時、自分のそばに神と仏(愛と慈悲)がなければ、本当に救いがないということになる。あきらめと無常だけが残る、無意味と無力感ばかりが漂っているようではいけない。「無常でした」がゴールであってはいけない。
要するに、自分の中に神がいるのか、愛があるのかということなのである。
そこに目を向けさせなくてはいけない。それが宗教の役割である。
呼び方や名前などどうでもいい。形式や方法を問うものでもない。心の中心がそれで定まればいいのである。愛と慈悲がそこに宿ればそれでいいのだ。
アッシジの聖フランチェスコは、一人になった時、そばに(自身の中に)神を感じたのである。だから「主よ、わたしを平和の道具としてお使いください」と祈ったのです。神と一つになり、彼は生きている意味を見いだしたのである。(救われた)
仏教は仏の心と一つになり、慈悲の心に生きる。人々の福祉の為に奉仕する。そのことに生きる意味を見いだそうとしている。それでこそ即身成仏と言えるのではないだろうか。空海や行基、多くの高名な僧たちは福祉事業や社会事業を行った。浄土はそのようにして実現されてゆくのだろう。
念仏は、阿弥陀仏(慈悲の心)に帰命することである。
阿弥陀仏の名前を呼ぶということは、阿弥陀仏(慈悲の心)の存在を肯定しているということである。
この世には、「慈悲の心があるんだ」と、私の心にも確かに「慈悲の心があるんだ」と・・・
(まるで、神が「私は有って有るものだ」、「私は慈悲だ」と言い聞かせているようだ。)
存在の根本を問いただす。
「神思う、故に我あり」という柳宗悦の言葉がすべてを言い尽くしていると思う。
神の愛と慈悲心があって、私が生かされているのである。
「信仰とは神に対する依頼ではない、神に即する内生である。」とも言う。

○ アッシジの聖フランチェスコ
「平和を求める祈り」
主よ、わたしをあなたの平和の道具(器)としてお使いください。
憎しみのあるところに愛を、
いさかいのあるところにゆるしを、
分裂のあるところに一致を、
疑いのあるところに信仰を、
誤りがあるところに真理を、
絶望のあるところに希望を、
闇に光を、
悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。
慰められるよりは慰めることを、
理解されるよりは理解することを、
愛されるよりは愛することを、わたしが求めますように。
わたしたちは、与えるから受け、ゆるすからゆるされ、
自分を捨てて死に、永遠のいのちをいただくのですから。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ここで理解しておくべき重要なことは、
フランチェスコはここに書かれている行為を、自分がやりますとは言っていないということです。
道具として自分を用いてくださいと祈っている。
ですから、愛や信仰や真理や希望をもたらす行為の主体は、あくまでも神なのだということです。
この祈りを通して、神が何を望んでおられるのか、どういうお方なのかが推察できる。
フランチェスコはただ、神の御心にかなうものとなりたかったのです。
この祈りは、フランチェスコの心の声、神の声なのである。
一遍は「念仏が念仏をする」と言った。それと同じように、祈りが(神の声が)神へと祈りを捧げているのである。人はただ器となって、自らを捧げているのである。
人の力でこの祈りが成就できるとは思わない。神が願い、神がやろうとしているのである。
フランチェスコの器を借りて、神が語り、神がなそうとしているのである。
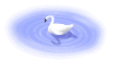
○ 愛の帰るべきところ
「神は愛である」、それだけを信じ、それだけに生きる。
神が神であるのは、愛だからである。神は「一」であり、不二である、未分の愛を持たれている。愛とは二つのものを一つにする力がある。二に分かれたとしても本質は不二である。神が内在する限り必ず愛し合って一つになり、「一」なる神へと摂取される。
神が神であるためには、愛でなければならない。でなければ人にも神にも喜びがない。
神は愛を完成させるために人を必要としている。愛は完全なものなので、永遠の世界において愛は既に約束を果たしている。愛は人を目的の地にいざなう、天国は用意されているのである。神の愛は「絶対の愛」である。だから必ずそうなる。神は愛であるというところに答えはある。
愛は愛であって、愛に帰着する。愛は変わることがない。愛は神なのである。
愛という「一」(未分の愛)に帰るのである。
○ 償い
神が愛だというのなら、なぜ地獄があるのだ?
結局、地獄というのは、神に愛がないからではない。愛されていないから、救われていないからではない。全き愛に摂取されながらも、自分が自分を許せないからである。自分で自分を裁いている。地獄に追いやっているのは、神ではなく自分なのである。(苦しくて愛を受け止められない)自分を捨てなければ、自分は救われない。
悪はやはり悪である。生きているうちに、なるべく償いの道を歩んだ方がいい。自分が苦しまないためである。
ここで、悪人に対しても愛するのか? という疑問が生じるかもしれない。
しかし、その人に対し憎しみをもって返すと、その人は帰る場所を失ってしまう。だから涙をもって返す。変わらない愛をもって接するがゆえに、その人は帰る道(悔い改める道)を見いだすことができるのである。神は元々すべてのものを愛しており(愛をもって創った)、その愛は変わらないのである。神が愛でなくなるということは決してない。
神が試練を与えるのは意地悪だからではない。その人を救うためである。
心の負担を無くし、愛のもとに帰りやすくするためである。
神はきっと愛して下さるだろう。(罪ではなく、あなた自身を)
愛を素直に愛として受け止める為に、生きているうちに良いことをすべきである。
心の中の負債を取り除いておくべきである。
苦労して障害児を育てたということは、私にとって良いことなのである。
悲しんでいる者は、慰められるのである。(マタイによる福音書 5章4節)
悲しんでいる人は素直に愛を受け止めやすくなるのである。
神の世界は二元ではない。地獄というものは永続するものではない。必ず「一」に帰る、愛の懐に帰る。一時的に経過として地獄のような償いの期間があるかもしれないが、最終的には神のもとに、仏の慈愛のもとに摂取される。救われてゆくのである。それが、神と仏の約束である。
人はみな仏性を備えており、いずれ如来となるのだ。
だから、誰であったとしても、どんなに馬鹿にされても、「決して人を軽んじたりしない」と言い続けた常不軽菩薩(釈尊)の姿勢は仏の意にかなう素晴らしいものだったのだ。

○ 何にゆだねるのか
確かに人は一人だ。その中心に何があるのか?
何もなければ不安になって当然である。消えてゆくだけの「無常」なる存在である。
しかし、私はなぜ存在するのか?
存在の根底に(私を生みだした)「愛」がある、それが神である。
だとすれば、愛によって生かされる、希望がある。喜びと平安がある。私の中から泉の如く愛が湧き上がってくるだろう。その愛にゆだねてゆけばいい。
喜びや幸福、天国や浄土は、「愛」によってしかもたらし得ない。
それならば、不安な道より、愛を信じ、愛を感じとり、愛に生きる道を選ぶべきである。
神と私、愛と私も「不二」でなくてはならない。「一」でなければならない。
その「一」(不二の愛)に帰るということである。
神は愛であるから、愛以外のものには干渉しない。愛に対して愛として働かれ、愛と一つになられる。
愛と神は「不二」である。
クリスチャンは「愛」に身をゆだねる。念仏者は阿弥陀仏、「慈悲心」に身をゆだねる。
○ 神と仏の世界観
この世は「二元」、無常の世界である。
善悪、自他、上下、貧富、苦楽、愛憎、美醜、生死・・・「二」の世界の中で苦しみ彷徨う。
しかし、仏教は慈悲によって「不二」の世界へと摂取されることを説く。善悪を分けて裁き主になるのではなく、あるがままを受け止め、無垢の世界に入ってゆく。未生の愛、未分の愛、不二の愛、本郷の愛に帰る。その「一」なる世界が浄土なのである。元々、仏の世界には愛しかなく、美と善しかない。それを知るために、「二」の世界を通過しただけなのである。(愛を知るために二つに分かれた)
「二」の世界で立てた愛の基準が、永遠の世界で生かされるのである。
本来、「二」に分かれたのは愛し合うためであり、調和をもって美を生みだすためである。
決して、闘争し、憎しみあい、分断するためではなかった。そうなってしまったのは、人間が罪を犯し、神から離れたからである。愛のない世界になったからである。
人は裁き主になるのではなく、ひたすら愛する存在となるべきである。
比較して愛するのではなく、誰であったとしても、涙を流しながらでも、ただ愛すればいいのである。「愛しかない」、それでいいのである。神がそうだからである。
愛は永遠に残される。それ以外のものはやがて消え去ってゆく。全ては愛に摂取される。「一」に帰る、神に帰るのである。
2025.3.30